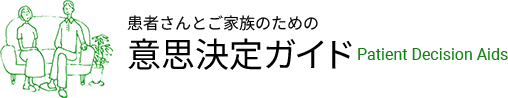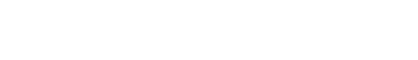| トピック | 乳がん、薬物療法(抗がん剤、ホルモン剤、分子標的薬)、妊孕性温存療法 |
|---|---|
| 対象 | 乳がんと診断され、妊孕性温存を行うか否かを検討している女性(患者)、妊孕性温存に関する選択を支援する医療者 |
| 選択肢 | 妊孕性温存を行うか、行わないか
・妊孕性温存を行う場合、どのような種類で行うか |
| 形式 | 冊子、ウェブ |
| 入手先 | https://decisionaid.jp/.assets/DA_oncofertility_2025.pdf |
| 開発者 | 開発者:紙谷恵子(山口大学大学院医学系研究科保健学専攻 講師)、伊東美佐江(山口大学大学院医学系研究科保健学専攻 教授)、医療監修:中村康彦(山口県立総合医療センター/生殖医療科 医師 統括副院長)、前田訓子(山口大学大学院医学系研究科消化器・腫瘍外科学講座/乳腺外科 医師)、田村功(山口大学大学院医学系研究科 産科婦人科学講座/医師))、作成協力者:前田梨恵(山口大学医学部附属病院/がん看護専門看護師)、本田紫子(山口大学医学部附属病院/乳がん看護認定看護師) |
| 意思決定がイドに関連する研究 | 1. 紙谷恵子, 伊東美佐江, 前田訓子. 乳がん診断後に妊孕性温存しないと意思決定した女性の体験. 日本看護科学会誌, 2023, 43, 602-611(https://doi.org/10.5630/jans.43.602).
【目的】:乳がん診断後に妊孕性温存しないと意思決定した女性の体験を明らかにする.【方法】:妊孕性温存しなかった女性19名に対し半構造化面接を行い,質的内容分析を行った.【結果】:質的データからは2つのテーマが抽出された.〈突然のがんと妊孕性の問題に人生設計の再考を迫られる〉では,予想外の診断にがんと向き合う準備が整わないなか,周囲の支えで妊孕性温存するかしないか自分の意思に向き合っていた.妊孕性温存しない意思決定の背景には明確な理由もあったが,断念せざるを得ない状況による諦めや,妊孕性温存以外の方法の模索もあった.〈自分が選んだ結果を生きる〉では,がん治療が一段落ついた頃から気持ちの変化が見られ,その後は前向きな気持ちが芽生える状況,様々な気がかりを残した状況の相反する体験が明らかになった.【結論】:妊孕性温存しない意思決定は,挙児希望や子どもの有無にかかわらず苦痛を伴う体験であった。 2. 紙谷恵子, 伊東美佐江, 前田訓子, & 齊田菜穂子. (2022). 乳がんに罹患した女性が薬物療法前に行う妊孕性温存の選択に対する意思決定支援: 文献レビュー. 日本看護科学会誌, 2022, 42, 501-508(https://doi.org/10.5630/jans.42.501). 【目的】国内外の文献をレビューし,乳がん女性が薬物療法前に行う妊孕性温存の選択に対する意思決定支援の実態と課題を明らかにする.【方法】MEDLINE,CINAHL,医学中央雑誌を用いて,2004年から2021年までの発表論文を対象に,キーワードは和文「乳房腫瘍」「妊孕性温存」,英文「Breast cancer」「Fertility preservation」とした.【結果】対象論文は8件で,意思決定に対する支援は「開発されたツールによる支援」と「医療専門職者によるコンサルテーション」に分類された.【結論】専門家の連携による支援効果は示されたが,意思決定支援ツールの効果は限定的で,情報提供の量や方法の更なる検討が示唆された.乳がん女性が行う妊孕性温存に関する選択は,様々な背景が関連しその影響は長期に及ぶため,医療者の連携と継続的支援を必要とする.わが国に応じた支援体制の構築が望まれる. |
| 国際基準による評価(開発者による評価)基準を満たしている数/この意思決定ガイドに該当する基準の数 | ①資格基準:6/6 ②認定基準:6/6 ③質基準:19/23 |
| 利益相反 | この意思決定ガイドの開発に関連して、開示すべきCOIはありません。 |
| 開発研究費 | 2021-2025年度 科研費(基盤C No.21K10684 研究代表者 紙谷恵子) |
| 特記事項 | この意思決定ガイドでは、乳がんの薬物療法が妊よう性(妊娠する能力)に与える影響や、妊よう性温存の種類、具体的な方法について解説をしています。また、妊よう性のことを決める上で大切なご自身の気持ちや価値観について、振り返り確認するための内容も含まれています。妊よう性のことを選択される上でお役に立てればと願っております。 |
| 意思決定ガイドを更新した年 | 2024年作成、2025年更新 |